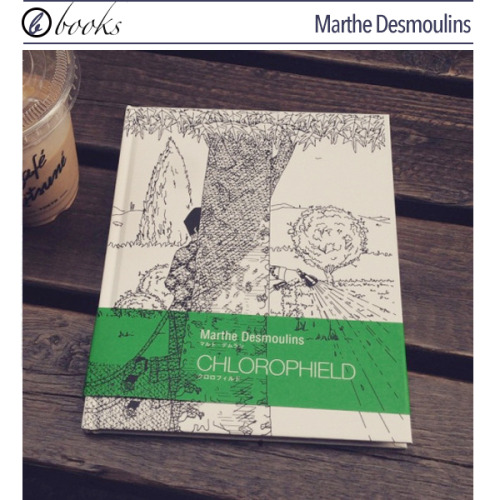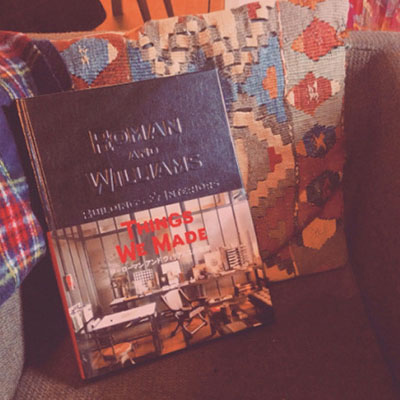『わたしを離さないで』『日の名残り』などの長編で有名なカズオ・イシグロの短篇集。
『わたしを離さないで』『日の名残り』などの長編で有名なカズオ・イシグロの短篇集。
音楽と夕暮れをめぐる五つの物語、という副題どおり、音楽をテーマにした5篇が収録されている。
老歌手、ジャズミュージシャン、チェリストなど、登場人物の扱う楽器はさまざまだが、共通しているのは「人生の夕暮れに差し掛かっている」ということ。
たとえば、『老歌手』に登場する往年の名歌手。
彼はハネムーンの地、ベネチアへ妻とともに再訪している。主人公でギタリストの「私」は、老歌手の依頼によりゴンドラへ同乗し、彼が妻へ捧げるセレナーデの伴奏をする。
こうして見るとただの良い話のように思えるが、実は、この夫婦は別れを目前としている。
愛情がなくなったわけではない。互いに深く愛しあいながらも、彼らには別れざるを得ない理由がある(その理由というのがまたバカバカしく、それが逆に悲哀を感じさせる)
だからこそ、彼が歌うセレナーデには、別れ行く妻への痛切な愛と悲しみが込められている。
『降っても晴れても』は唯一、音楽家の出てこない作品。
主人公は冴えない独り者の英語教師で、成功者である昔馴染みの友人に頼まれ、彼の妻エミリに会いに行く。
友人はエミリとうまくいっておらず、惨めな境遇の主人公と自分とを比較させることで、彼女の愛情を取り戻そうとしていた。
だが、主人公がうっかり覗き見たエミリの手帳を損傷してしまったことから、事態はとんでもない方向へと転がりだしていく……。
コメディ的要素が強い作品だが、どこか物悲しくもあるのは、この話の登場人物がみな「失いつつある何か」、あるいは「すでに失われた何か」への思慕を抱いているからだろう。
とはいえ、大鍋で煮こまれた革靴のシーンは、やはり笑ってしまう。
他にも、チェロを弾かないチェリストとその弟子の話や、売れるために整形をするサックス奏者の話など、音楽にまつわる色彩豊かな短編がおさめられている。
どの作品にも静かな哀愁が通奏低音のように響いているが、読後感は不思議と軽い。
夏の夕暮れに、ジャズでも聴きながら読みたい一作である。
 夏になると読み返したくなる本、というものがある。
夏になると読み返したくなる本、というものがある。
春や秋や冬が凡庸だというわけではもちろんないが、夏という季節は、やはり人にどこか特別な感慨を抱かせる。
アスファルトに落ちた濃い影や、煩いほどの蝉の声。波濤の轟きと、足の下で砂が流れていくあの奇妙な感触──。誰しもが、心の奥に特別な夏の風景を持っている。
今回紹介する『レクイエム』も、そんな夏の光景を思い起こさせる小説だ。
舞台は七月のリスボン。主人公である「わたし」は、とある詩人(のちに、この相手はポルトガルの巨匠・フェルナンド・ペソアだとわかる)と待ち合わせをしている。
待ち合わせが昼の12時ではなく、夜の12時だということに気づいた「わたし」は、あてどもなく灼熱のリスボンをさまよい歩く。
そこで「わたし」は、死んでしまった友人や恋人、若き日の父親などの死者たちと出会う。
だが、それらの邂逅は決してドラマティックではなく、ごくさりげない、当たり前の日常のように描かれる。
そうした出会いと別れの中には、死者だけでなく市井の人々も含まれるのだが、生者であるはずの彼らが本当は亡霊なのかも知れず、
はたまた、語り手である「わたし」自身、本当に生きているのか、死んでいるのかすら、わからなくなっていく。
こう書くと、非常に読みづらい物語のように思われるかもしれないが、決してそんなことはない。
幻想の中に深く沈み込むような読み口は心地よく、軽い酩酊感とともに見知らぬ土地を見て回る楽しさを味わえる。
さらに特筆すべきは、この本が「美味しい」描写に満ちていることだ。
巻末に章ごとの料理一覧がまとめられていることからもわかるように、「わたし」は行く先々で様々な料理を口にする。
インゲン豆のスープであるフェイジョアーダ、魚介類でつくるパン粥、子羊の肉と臓物のシチュー……、日本人には馴染みの薄いものばかりだが、どの皿も旨そうで思わず喉が鳴る。
なかでも、国立美術館のバーテンダーが供するカクテル(ウォッカが四分の三、レモンジュースが四分の一、ミントシロップ小さじ一杯を、氷と一緒にシェイクしたもの)は印象的だ。
リスボンを訪問する予定はないが、もし行く機会があれば、きっと国立美術館のカフェへ足を運ぶだろう。
たとえ、大統領にカクテルを作ったという、そのバーテンダーはおらずとも。
著者のアントニオ・タブッキはイタリアの幻想作家で、代表作として上記の『レクイエム』のほかに、映画化もされた『インド夜想曲』や『遠い水平線』などがある。
夢と現実のあわいを縫うように描かれた作品は、幻想文学でありながらも、どこかリアルな手触りを持って読者に迫ってくる。
タブッキの小説は五感を刺激する。
それは、たとえば肌を焼く灼熱の日差しであったり、蕩けるようなスープの味であったり、過剰に拡大されたヒエロニムス・ボスの絵だったりする。
だからこそ、読者はまるで自分が見てきたかのように、小説内の光景を思い浮かべることが出来るのだ。
優れたフィクションは現実に勝る。
夏が来るとタブッキを読みたくなるのは、そうして刻まれた記憶を反芻するためなのかもしれない。
 2013年、世界で最も素晴らしいヒューマンドラマが誕生した。
2013年、世界で最も素晴らしいヒューマンドラマが誕生した。
同年のSXSW(サウス・バイ・サウスウェスト)映画祭でのワールドプレミア以降、世界中で30もの映画賞を受賞したこの作品は、
観る人を感動させること間違い無しのヒューマン・ドラマ映画である。
ネグレクト(虐待や育児放棄)によって傷ついた子供たちを、一時的に預かる短期保護施設「ショート・ターム」。
そこで働く主人公のグレイスが、ガラスのように繊細な子供たちとの付き合い方や、自身との向き合い方、恋人との距離など、
様々な問題に対し、悩み苦しみながら自分なりの答えに近づいていこうとする物語。
物語の中心となる、一人の少女ジェイデンの入所をきっかけに、グレイスは自身が封印していた過去のトラウマと向き合うことになる。
施設の子供たちは、社会に置き去りにされたような不安、愛されないことへの悲しみ、暴力に対する恐怖など、押しつぶされそうな心の闇を持って過ごしている。
彼らのその痛みは、ネグレクトを経験していない人々にとっても、少なからず共感することができると思う。
ストーリーはもちろん素晴らしいが、ここでは演出の素晴らしさを強調したい。
闇を抱えた子供達の心と対照的に、映画全体のカラーが暖色系を多く使った、温かみのある配色にしていることが、この映画が優しさに溢れた作品であることがわかる。
施設の子供達の部屋のインテリアや、服装においては、それぞれの個性が見て取れるし、グレイスの自宅も、良く観てみると、
子供達が書いたような絵画が並んでいて、細やかな演出にも気を配っている様子分かる。
そしてなにより、登場人物の一人になったような視点で観れるのは、この映画が手持ちカメラで撮影されていることによると思う。
印象に残るシーンとして、プロローグとエンディングをここで取り上げたい。それぞれのグレイスの心境の違いを、みなさんはどんな風に感じるだろうか。
監督であるデスティン・ダニエル・クレットン氏は「こういう仕事を選んで、児童養護施設で働くスタッフこそ、本当のヒーロー」とインタビューで語っている。
ヒーローとは、弱いものの心に寄り添い、守り、自身も傷を負って悩み苦しみ、最後には希望を見出して未来へとそれをつなげていける存在。そんな人物。
『ショートターム』次回作として『The Glass Castle(ガラスの城の子どもたち)』が決定している。
ジェニファー・ローレンスが主演と製作を務めるということもあり、期待大の注目作品となりそうだ。
 人間嫌いとは何か。
人間嫌いとは何か。
自分を理解してもらえないこと、他人を理解できないことの先にある感情。
他人(自分)をコントロールできないことへの絶望感。
モリエールの『人間嫌い』は、読者が主人公のアルセストに感情移入するかどうかが分かれる作品だと思う。
人間は誠実であるべきで、欺瞞は恥ずべき行為、それがわからない奴らはみんな馬鹿だ。
というようなことを言ってしまえる若さゆえの潔癖によって、上流社会の不義・不正に悩み、絶望したのち自らを社会の外に追いやろうとしてしまう。
虚礼やお世辞に対して過剰に反応し、すべての欺瞞に絶望と怒りを感じるアルセストの心情と、自身の理想に反しているものの想いを寄せる、
コケットな未亡人セリメーヌへの苛立ち、彼を取り巻くすべての欺瞞に満ちた人々の滑稽さと人間模様を喜劇的に描いた傑作である。
アルセストとは一体誰か。
アルセストは単に正義の人ではないことが、本書の後半に明らかになる。 正義感と信念を振りかざし、他人を罵倒していた人間が、
自身の傷ついた心を憎しみに変えた時、他人を利用しようとする、というのはよくある話である。
よくある話ではあるが、読み流してしまいそうになる程サラッと書かれているのが素晴らしい。
アルセストは、人間関係に希望をもつ、幼さの残る若者である。
それは社会人となった今、彼の友人フィラントのように振る舞う私たちの以前の姿とも言えなくもない。
信念を持ち、人に期待をし、自らを顧みない自分である。
『人間嫌い』は、道徳的なのは誰か。人間的なのは?
いろんな面から人間という生き物を考えさせられる、とても”人間らしい”一冊である。
※生涯で一度は読んでほしいシリーズ その1
『最後の物たちの国で』ポール・オースター
BOOKS
 主人公のアンナは、消えた兄を探しに「最後の物たちの国」へ行く。
そこでは、赤ん坊は生まれず、人々は死にゆき、物も言葉も消えてゆく世界。
その国に降り立った瞬間に、彼女は全てを失ってしまい、為す術もなく途方に暮れ、その国で日々を過ごしてゆく。
最低限生きていけるだけの物資を買うための、ゴミ漁りというような職。
人々は生きるために自分のことのみに専念し、犯罪は蔓延していく。
主人公のアンナは、消えた兄を探しに「最後の物たちの国」へ行く。
そこでは、赤ん坊は生まれず、人々は死にゆき、物も言葉も消えてゆく世界。
その国に降り立った瞬間に、彼女は全てを失ってしまい、為す術もなく途方に暮れ、その国で日々を過ごしてゆく。
最低限生きていけるだけの物資を買うための、ゴミ漁りというような職。
人々は生きるために自分のことのみに専念し、犯罪は蔓延していく。
アンナは、腐敗した街で消えていく物や人に触れ、恐れと餓えに翻弄された人々の狂気に触れ、
消え入りそうな自身の個としての存在の中に、わずかに感じ取った想いを別れた故郷の友人に綴る。
私にとって、ポール・オースターは「幽霊」にとりつかれた作家だと感じることがある。
幽霊とは、死んだ者たちの意識であり、人々の中にあるゴースト(魂)の存在である。
オースターは、人々の幽霊を感じ取り、その存在自体を個として扱うといった表現を小説に展開させることが多いと思う。
この作品においては、まさに死んだ物がさまよう国で、幽霊たちはわずかな記憶や欲望、意識を基に個を形成し生きているかのようだ。
あとがきによると、ポール・オースター作品の中で、唯一女性の声で語られる作品であり、
その声はオースター自身に1970年から聞こえ始め、何年もの間断片的に聞こえてきたという。
そして、その後はっきりと彼女の声が聞こえ始め、ほとんど「聞き書き」のようにして書き上げた作品だということだ。
ある意味で、この作品は巡礼の旅に出かけた少女の話と言えるかもしれない。
80年代、 ポール・オースターは「限りなくゼロに近づいていくことによって、何が見えてくるか」を彼の作品の主なテーマとしていたという。
これは直接的にその題材を主とした作品であり、何もかもがなくなってゆく世界で生きて行く人間の姿を、生々しく描いている。
正直いうと、私は昭和初期の日本の文学や、こういったひどく貧しい生活を続ける話がものすごく苦手である。
ましてゴミを漁り続け、生きる希望を見出せず、痩せこけあとは死んでいくだけだという状況を読む、という苦行は何より恐ろしい。
しかし、これは現代のどこかの国であり、とある日本という国であり、私自身である。
訳者である柴田元幸氏は、あとがきの最後にこう綴っている。
「不思議なことに、オースターの全作品の中でも、ある意味で一番「希望」を感じさせる一作です」
さて、全てをそぎ落とされた「最後の物たちの国」へ足を踏み入れて、幽霊になったあなたは何を見る?
 小説において、食の描写はとても重要である。どんな単純な料理であっても、その表現の仕方によって印象がずいぶん変わってくる。
下手するとその小説の内容よりも、食に関する一文だけがずっと鮮明に記憶に残ることもありえる。
小説において、食の描写はとても重要である。どんな単純な料理であっても、その表現の仕方によって印象がずいぶん変わってくる。
下手するとその小説の内容よりも、食に関する一文だけがずっと鮮明に記憶に残ることもありえる。
今日はそんな食の文学的表現を題材にした著書、柴田元幸の『つまみぐい文学食堂』を紹介したい。
この著書は「メニュー」から始まり、「前菜」「魚料理」「肉料理」「スペシャリテ」「飲み物」「デザート」と順に、
世界中の著書の中から柴田氏が厳選した「食」にまつわるセンテンスを抜き出し解説するといった内容である。
世界中のあらゆる文学テーブルから、少しずつ拝借しているような形になっており、まさにつまみ食い。
引用文はほぼ柴田氏の翻訳なので、実に表現が滑らかで読みやすく、文章から食べ物が転がり出てくるようである。
想像の味覚が踊りだすほどのうまそうな料理がでてくるのかと思いきや、ほとんどの場合、
舌の上で食材に閉じ込められた暗闇が広がるような料理だったり、身の毛のよだつような料理ばかりである。
例えば、ニコルソン・ベイカーの著書『下層土』ではジャガイモが取り上げられている。
主人公が訪問先で出会ったジャガイモの表現において、この世でこんなに恐ろしいジャガイモとの出会いなど、想像もつかなかかった。
取り上げられた引用を読んだ後で、しばらく私はそのジャガイモの顔をしていたに違いない。 ニコルソン・ベイカーの視点はとにかく変わっている。
「変わっている」という点で小説家の中で右に出るものがいないんじゃないかと思うほど。
『下層土』はまだ未読だけれど『中二階』は是非読んでみてほしい一冊である。
※これは、またいずれブログに掲載します。ニコルソン・ベイカー『中二階』
また、レイチェル・インガルズの『ミセス・キャリバン』では、主人公ドロシーがカエル男との出会いで恐る恐る差し出した、セロリの描写の引用もまた素晴らしかった。
そして、キュウリでもなく人参でもなく、セロリだったことの意味を、柴田氏は推測し解説している。
登場する食材は、それぞれストーリーとは関係ないところで、象徴的に取り上げられていることが多いように思う。
そこにどんな意味が込められているのか、どうして「セロリ」だったのか、なんていうことを想像し推測するのが「つまみぐい文学」の面白さとなっている。
全体を通して読んだ感想としては、前菜までの文学料理はとても美味しくいただけた。
肉料理からの展開は、少々消化不良をおこしたという気がしなくもない。
しかしこの著書を読んで、これから読みたい本を発見できたという点と、食に関する文化的・歴史的背景や、
人と食のつながり、またそれらにまつわる文学的表現方法など、視点を変える、あるいは掘り下げて読むということを学んだ気がする。
最後に、私の記憶の中での絶品文学料理を一つ。
言わずもがな、村上春樹は食べ物の描写に関しても大変定評のある作家である。
彼の小説に出てくる料理は、料理本としても発行されているほど。
私も彼の小説にでてくる料理のファンである。
特に『世界の終りとハードボイルドワンダーランド』にでてくる、キュウリのサンドウィッチは、主人公といい関係になりそうな女性が、彼のために作ったものだ。
それはいたって普通のキュウリのサンドウィッチなのに、きゅうりの厚さ、切り口、塩やバターの塩梅。どれをとっても完璧なのである。それはどんなにおいしいのだろうと自分でも作ってみたりする、が、未だに彼女の作るキュウリサンドイッチには到達してないような気がしている。
そうだ。『バベットの晩餐会』もいいな、と思ったけれど、こっちは料理が主体だから、つまみぐいにならないか。
※『バベットの晩餐会』後日ブログに掲載。
それでは、みなさま。
よい文学料理を。ボナペティ。
『CHLOROPHIELD 』
マルト・デムラン&フランク・ドラ
BOOKS
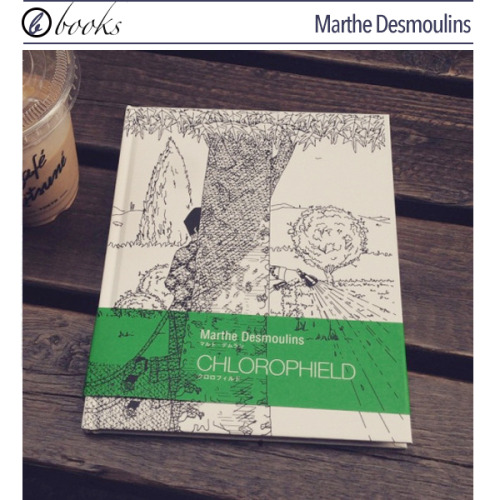 マルト・デムラン&フランク・ドラ『CHLOROPHIELD -クロロフィルド-』出版イベント、来日パーティーへお邪魔して来た。
マルト・デムラン&フランク・ドラ『CHLOROPHIELD -クロロフィルド-』出版イベント、来日パーティーへお邪魔して来た。
マルト・デムランはH.P.FRANCE Bazar et Garde-Manger(バザー・エ・ガルド・モンジェ)のバイヤーであり、彼女のお店に並ぶ商品は、全て彼女が選んできたお気に入りのものだそう。
Bazar et Garde-Mangerは「Bazar = あらゆるものが溢れる雑貨屋. Garde-Manger = 冷蔵庫がなかった時代の、
食べ物を保存しておくための貯蔵庫過ぎ去っていく時間の中で、一生とっておきたくなるようなもの」という意味だそうで、お店の中もまるで誰かの素敵な住居のよう。
彼女の選ぶファブリックや雑貨は、少女の頃大好きで大切にしていた宝物のようなアイテムが溢れている。
大好きな物を集めて並べたようなごちゃ混ぜ感がありつつ、部屋の中で統一されている不思議な空間。
一人の少女の成長の中に見る、記憶と現在が混ざっているような感覚に陥る。
その一つを手にとって、その物語ごと商品を購入していくような、なぜか彼女の店にはそんな感覚を呼び起こすファンタスティックなときめきがある。
本日発売のライフスタイルブック『CHLOROPHIELD -クロロフィルド-』は、『DECOLOREE -デコロレ-』『POPOTTE -ポポット-』に続く3部作目の最終章。
彼女のパートナーである、フランク・ドラとのフランス・プロヴァンスの生活がたっぷりと紹介された素敵な本だった。
プロヴァンスの小さな村、ペルヌ・レ・フォンテーヌでの暮らしは、ハーブや野菜などの草木に囲まれ、古い町並みの中の噴水、美しい自然などが紹介されている。
また、フランクの挿絵は、ユーモラスなタッチで描かれているのも面白い。彼のチャーミングで優しい人柄がそこに現れているようだった。
限定発売なので、是非バザー・エ・ガルド・モンジェへ足を運んで手にとってみてほしい。
そして、お店に行くときっとその世界に物語を感じるはず。
『Roman and Williams』
ローマン&ウィリアムスの思考
BOOKS
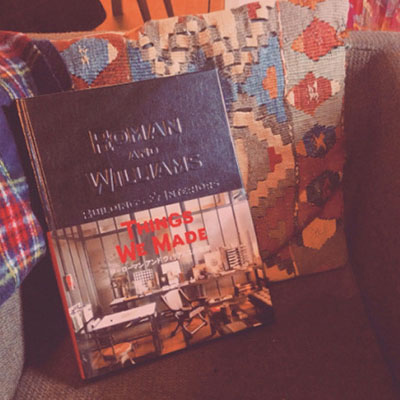 NYでいま一番人気のインテリアデザイナーといっても過言ではない、スティーヴン・アレッシュとロビン・スタンデファーの手がけるデザインチーム、ローマン&ウィリアムス 。
NYでいま一番人気のインテリアデザイナーといっても過言ではない、スティーヴン・アレッシュとロビン・スタンデファーの手がけるデザインチーム、ローマン&ウィリアムス 。
昨年、彼らの10年間の仕事を網羅した作品集の完全和訳版が出版された。
手に取るとずっしりと重い大型版には、彼らの手がけたNYのホテルやレストラン、FACEBOOK社の食堂などの写真が詰まっている。
それらは非常にファッショナブルで洗練されているが、どこか親しみを感じられ、実に不思議な調和でデザインされている。
その空間に一歩足を踏み入れた途端、映画の中の登場人物になったかのように、個人の中にスッとストーリーが感じられることだろう。
そう、彼らの原点は映画の舞台セットを手がけるところからスタートしている。
映画『ズーランダー』での仕事以降、ハリウッド俳優の自宅や、ホテルの内装デザインを手がけるようになり、今では世界中で仕事を受けるようになった。
彼らの名義であるローマン&ウィリアムスは、スティーヴンとロビンそれぞれの祖父に由来する。
ヒッピーな両親に育てられた彼らにとって、両親のスタイルとは、相反する祖父の存在が大きく影響してきたことは間違いない。
そしてその家族の中に存在したのであろう、相反する時代の背景こそ、彼らのアートだと言えるのかもしれない。
彼らはブレスリンとエース・ホテルを表す言葉として、こう言っている
「2つの相容れないストーリー、力のかぎりにぶつかり合う2頭の雄牛」。
計算され配置された空間ではなく、 ストーリー性のある空間の、自然に発生したかのように見える調和こそ、彼らの作品であり、彼ら自身の歴史なのだろう。
そこに見え隠れする「誰か」のこだわり、主張、そしてストーリーをデザインする。
単にパーフェクトな空間を完成させるというのではない、そこにアーティスティックな押し付けでは決してない、人を惹きつけてやまない魅力を空間の中にポツンと置いていくような表現。
デザインと何度も書いてきたけれど、おそらく彼らは、デザインという概念から離れた芸術を生み出していると言える。
ああ、エースホテルへはいつ行けるんだろうなぁ。
今日のことば:
「美は細部に宿る」ミース・ファン・デル・ローエ
 『わたしを離さないで』『日の名残り』などの長編で有名なカズオ・イシグロの短篇集。
『わたしを離さないで』『日の名残り』などの長編で有名なカズオ・イシグロの短篇集。